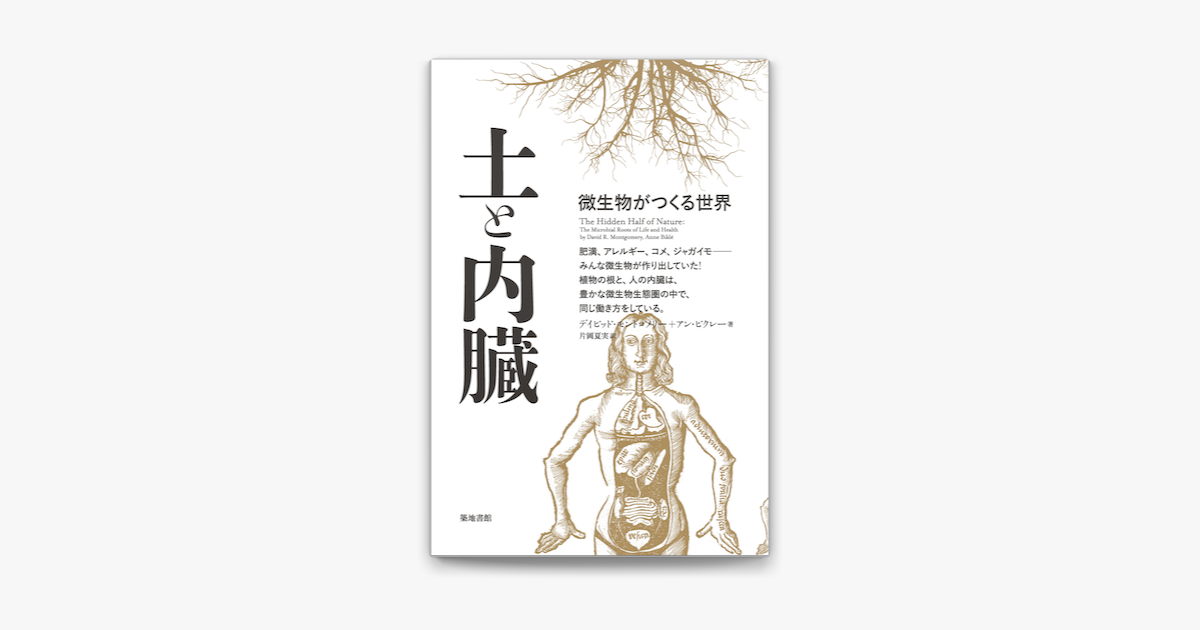本書のタイトルを見て、普通はこう思うだろう“土と内臓、この遠く離れたふたつのものがどう結びつくのかと。ただ、遠いようでいて、なにか近しいものがあるのではないかと直感的に感じるのも事実だ。そして、その直感は正しい。副題にもあるとおり“微生物”という観点を持ち込むことで、土と内臓(特に大腸)はパラレルに語ることが可能になるのだ。
この書物に説得力を与えているのは著者がD・モントゴメリーという土壌学者とA・ビクレーという生物学者の共著ということ、さらにこのふたりが夫婦であって、彼らの菜園づくりと癌を克服した経験に基づいているという事実だろう。特にD・モントゴメリーは『土の文明史』という、土の肥沃度という観点から文明の栄枯盛衰を捉え直したベストセラーを著した実績も持っている。
ふたりはシアトルに土地を購入し、そこで庭づくりを始める。ところが、その土地は土壌学者と生物学者が暮らすには相応しくない不毛の地だった。彼らは、庭の土壌改良をすべく落ち葉や大量のコーヒーかす、動物園からもらい受けた糞などの有機物を大量に投入していく。しかし、それらはみるみる嵩を失って、黒い肥沃な土へと変化していく。その劇的な変化を演出しているのが、目に見えない微生物たちだった。
それに気づいた夫婦は、微生物のめくるめく世界を旅し、その成果を読者に余すことなく伝えてくれる。それは地上の生物たちよりもはるかに多様な微生物群が途方もない共生のネットワークを構成し、植物の生育に止まらず、地球環境に大きなインパクトを与えている、いやむしろ微生物が生み出した現在の環境に適応して私たちが存在しているという事実だ。
一方で、妻のA・ビクレーは子宮癌を生き延びた経験を通して、人体における微生物の働きの大きさに気づかされる。そして明らかになるのが、多様な微生物が大量に生息する大腸がいかに土と似た働きをしているかということだ。
植物の根は微生物に有用な物質を放出して、彼らを引き寄せ、代わりに多様な微生物の代謝物を利用して、必要な栄養を得て、病気から身を守っている。そのネットワークとコミュニケーションは複雑かつ巧妙で、“根圏”とよばれる共生圏を作り出している。一方で、空気中の窒素を莫大な石油エネルギーを使って固定する技術が第一次大戦時に開発された(それが化学兵器開発の副産物として生まれたのは皮肉なことだ)。これによって、植物を劇的に成長させる窒素肥料による化学的農業は世界の主流となった。しかし、“根圏”のバランスを極端に崩す化学的単一栽培農業は、結果として病気の発生につながり、それを抑制するための農薬とセットにならざるを得ない。
これは完全に腸内細菌叢の話とパラレルだ。腸壁のひだや粘膜は腸内細菌にとってすごしやすい環境を提供し、植物の根と同じように、有用な細菌が好む物質を分泌して彼らを引き寄せる。一方、細菌は短鎖脂肪酸をはじめとする私たちに有用な代謝物を提供する。腸内細菌叢は、人それぞれ無数の多様性を持ち、それが私たちの人格にすら影響を及ぼしているともいわれている。この複雑で巧妙なネットワークに抗生物質が投与されたらどうなるだろう?ターゲットにしている人体に害を及ぼすとされる細菌だけでなく、腸内の細菌が織りなす多様性そのものを破壊しかねない。
化学肥料や抗生物質が、世界の人口を支え、沢山の命を救っていることは紛れもない事実だ。しかし、微生物が織りなす複雑な世界を知ってしまったからには、長い年月を生き延びたこのシステムを強化し、地球と体のレジリデンスを高めることこそが最良の方法に思えないだろうか。そうした世界の見方の転換を迫るだけの力を秘めた書籍だ。